芥川賞を受賞し、本屋大賞にもノミネートされた、宇佐見りんさんの小説「推し、燃ゆ」の感想と考察を記載。
なお、ネタバレが含まれますので、この記事は読了後に読むことをおすすめします。
本考察と関係ないが、本の表紙の、少しグレーがかったピンクと、主人公が上からぶら下がっているデザインがとても好き。
あらすじ
主人公あかりは、自身の人生に満足を感じられず、日々を推し活(推しを応援する活動)に捧げる高校生。彼女の生活は、推しであるアイドル上野真幸に対する一方的な愛情と尊敬によって支えられている。しかし、ある日、彼女の推しアイドルがファンを殴打したというニュースが流れ、彼女の世界が揺らぐ。この事件は、彼女にとっての推しとの距離感、そして推し活に対する献身がもたらす心理的な影響を探るきっかけとなる。
推しに共鳴し、自分の理想像として愛で始める。
この本に限らず、推し活している人には愚問だと思うが、推し=叶わぬ恋というような単純なものではない。そのように単純化して接したりすると、推し活している人に怒られるか、相手にされないままで終わってしまうだろう。
あかりの場合は、4歳まで遡る。4歳のときに劇で見た推しがピーターパンを演じていたが、劇中何度も「大人になんかなりたくない」と言い、それに対して、あかりは「これは自分のための言葉だ」と共鳴するところから始まる。
重さを背負って大人になることを、辛いと思ってもいいのだと、強く肯定してもらった気がして、自分が推しとつながった感じを覚える。
その後、時は立ち、主人公が高校生になり、推しはアイドルグループとして活動する。推しは、外面は落ち着いた雰囲気のある青年になったものの、ふとした瞬間に見せる眼球の底から何かを睨むような目つきは幼い頃と変わっていないと、あかりは感じる。芸能界に入って自分を追い込み続けた人にしか出せない光を感じ、自分の人生がうまくいっていない(勉強できない・バイトも上手くこなせないなど)中での理想像として推しを愛で始める。
単に理想像というだけではなく、推しには、断じる口調ばかりで誤解を招くことが多いという人間らしさもあり、その点にも自分と似ていると感じるあかりは共鳴する。むしろ自分との共通点があると思ったからこそ、芸能界に入って重さを背負って大人になっている、人生の先輩でもある推しを英雄視したのだろう。
自分にとって非の打ちどころがないほど、完璧なアイドルを推す場合もあると思うが、完璧なものは崇拝の対象となりがちで、一方で自分も共感できる、無邪気な一面・おっちょこちょいな部分など少し弱点があるアイドルの方が、ファンは親近感が湧き、より推しに対してのめり込みやすい(という表現は言葉が足りないが)気がする。
綿棒の意味
「推し、燃ゆ」ではクライマックスとして、あかりが綿棒のケースを床にぶちまけるシーンが描かれる。
推しを推さないあたしはあたしじゃなかった。推しのいない人生は余生だった。 (中略) 彼がその眼に押しとどめていた力を噴出させ、表舞台のことを忘れてはじめて何かを破壊しようとした瞬間が、一年半を飛び越えてあたしの体にみなぎっていると思う。
「推し、燃ゆ」宇佐見りん
推しは、ファンを殴打したという本当かどうか分からない出来事は、あかりにとっては、今まで重さを背負って(社会とある意味迎合して)大人として生きてきた推しがついに、自分の殻を破ったというある種の勇気を与えてくれるものだったのではないだろうか?
とはいえ、その結果として1年後に推しはアイドルグループ解散により、アイドルから普通の人になるという結末を迎える。
推しがファンを殴打したという行動は、あかりに勇気を与え、自分も今のうまくいかない人生をぶち破ろうと試みるのだが、結局は、片付けるのが安牌な綿棒を一瞬のうちに選んでしまう。
そして、そうした自分に一瞬のうちに気づくものの、「これが自分か。社会や世間体をぶち破って自由気ままに生きるまでは出来ないし、死ぬ勇気もないけれども、余生を生き続けないといけない」という、半ば絶望・諦観とともに、それでも前に進んでいくという覚悟が描かれている。
推しのように、社会からの圧力に対して自分の気持ちに忠実に行動したとしても、結局は社会に潰されてしまうし、かといって、自分は推しほどの勇気ある行動はできずに、その場合は現状は何も変わらないが、それも含めて自分だと自己肯定まではいかないが自己理解したという感じだろうか。
推しに勇気付けられて自分も殻を破れて、その後の人生が好転しましたというハッピーエンドではなく、あくまで観察的に、推し活をしているあかりの、感情や行動を述べ続けて終わっているところが、現実味があって、個人的にはとても良かった。純文学という感じである。
様々な推しとの距離感
感想はここまでなのだが、他に気になった点を抜粋
携帯やテレビ画面には、あるいはステージと客席には、そのへだたりぶんの優しさがあると思う。相手と話して距離が近づくこともない、あたしが何かをすることで関係性が壊れることもない、一定のへだたりのある場所で誰かの存在を感じ続けられることが、安らぎを与えてくれるということがあるように思う。推しを推すとき、あたしというすべてを懸けてのめり込むとき、一方的ではあるけれどあたしはいつになく満ち足りている。
「推し、燃ゆ」宇佐見りん
一口に推しといっても、さまざまな距離感の推し活があり、あかりの場合は、ある程度の距離感を持って推しを愛でている状態が一番心地よく満ち足りている。
作品は異なるが、綿矢りさ著「蹴りたい背中」では、同様に熱烈な推し活をしている「にな川」は、なんとしても実物の推しであるオリチャンに近づきたいと願い、最終的にコンサートでオリチャンに近づくことができたものの、にな川からしたらonly oneであるオリチャンが、実際には逆からしたらone of themである現実を目の当たりにしてしまい、自分の中の推しが崩壊し、夢(という表現が正しいかは微妙だが)から目が覚める。
自分は推し活をしたことがないのだが、周りで推し活をしている人はいて、それぞれ様々な距離感の人たちがいて、推しに対する感情も、恋愛感情・純粋な応援・愛しい・理由なんてない(これが一番多いと思う)など、様々で、推しって一口に言っても奥が深いなと思わされている。
しかも推し活に関して言えば、年代も10代から70代を超えてまで、恋愛と同様に幅広い。
世間には、友達とか恋人とか知り合いとか家族とか関係性がたくさんあって、それらは互いに作用しながら日々微細に動いていく。常に平等で相互的な関係を目指している人たちは、そのバランスが崩れた一方的な関係性を不健康だと言う。脈ないのに想い続けても無駄だよとかどうしてあんな友達の面倒見てるのとか。見返りを求めているわけでもないのに、勝手にみじめだと言われるとうんざりする。あたしは推しの存在を愛でること自体が幸せなわけで、それはそれで成立するんだからとやかく言わないでほしい。お互いがお互いを思う関係性を推しと築きたいわけじゃない。
「推し、燃ゆ」宇佐見りん
推しの世界観が理解できないと、これは推しに限らずだが、どうしても一面的な見方で接しがちになるので、こうした隔たりはどうしても生じてしまいそう。
ただ、本は一つの手段ではあるが、本を読んだりしてこうした世界や価値観があるんだと理解することは、相対した時に色眼鏡なくありのままをまず認識する際に役立つと思う。







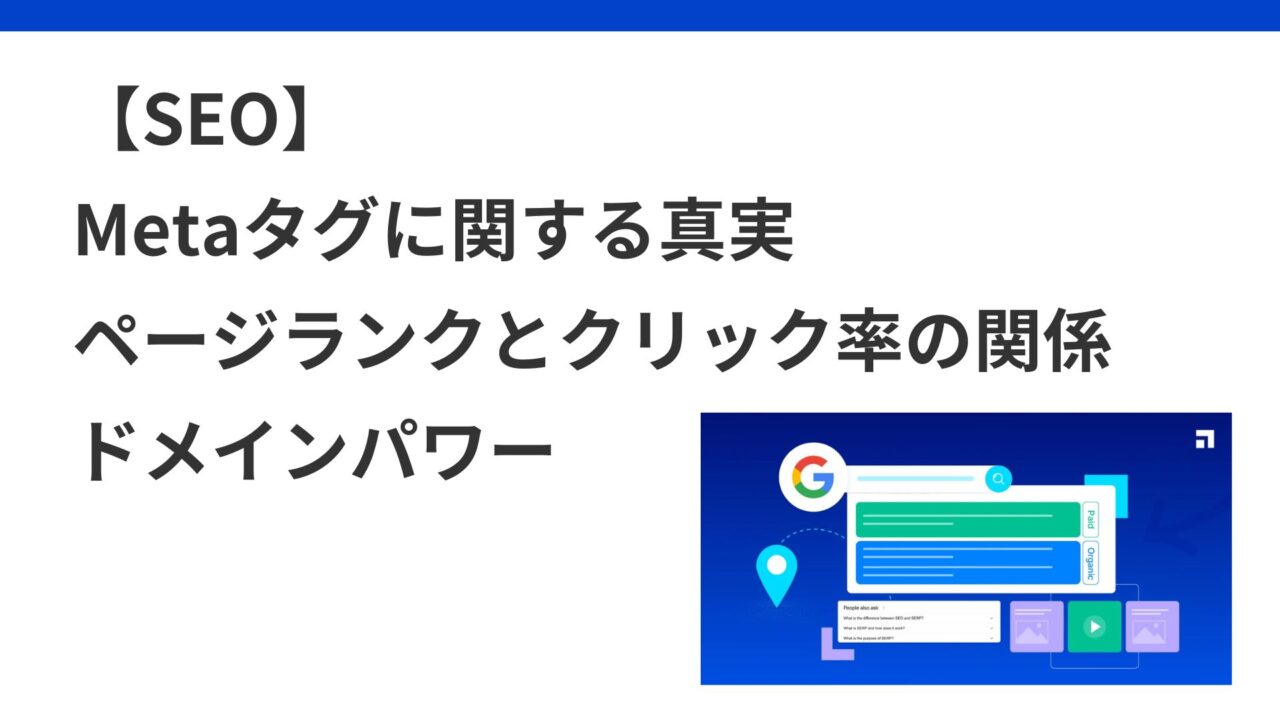

コメント