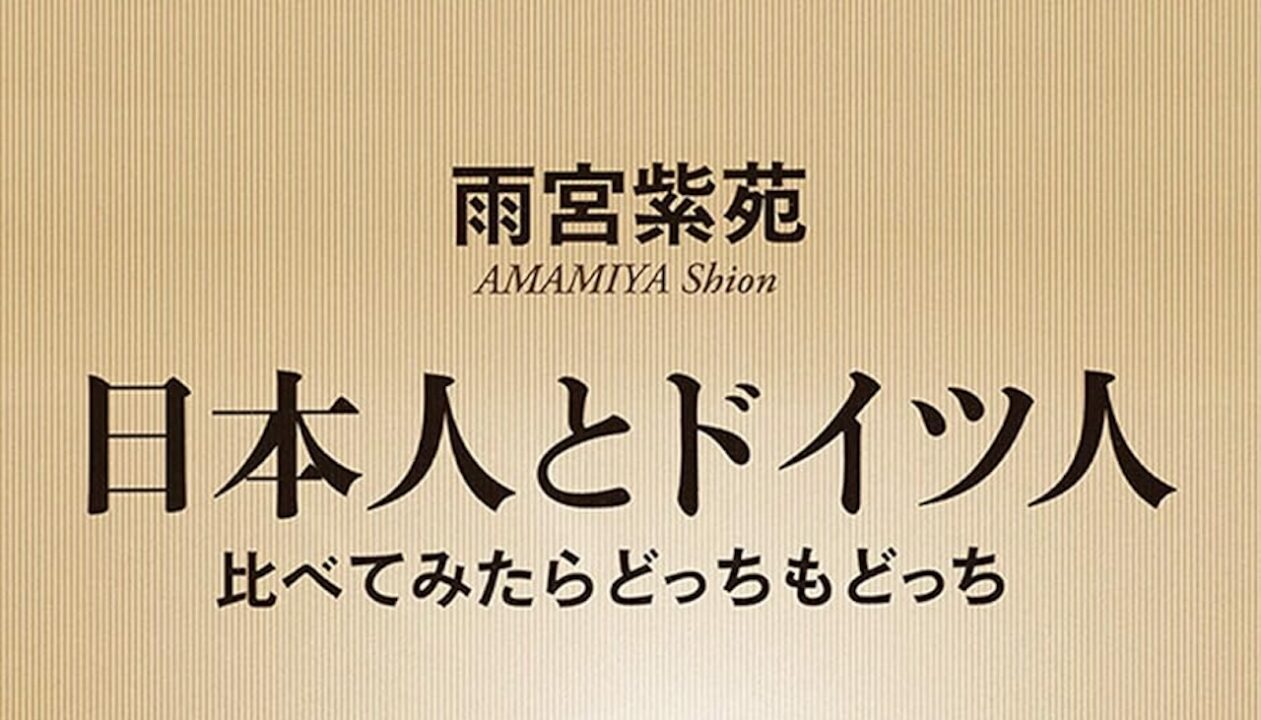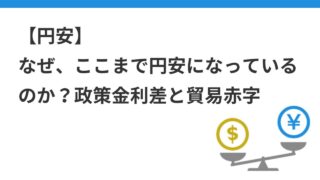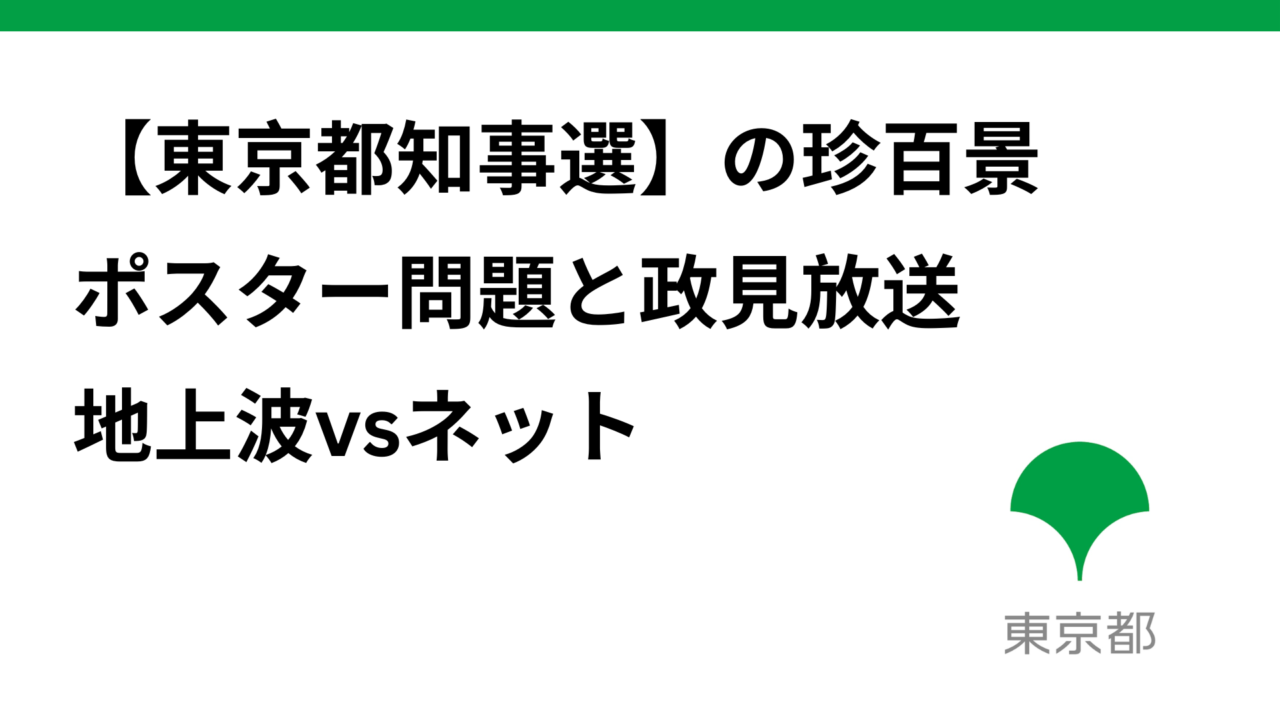はじめに
たまに、Xのタイムラインで流れてくる「Books&Apps」というWebメディアの記事をクリックして読むことがあるのだが、サイトに記事を寄稿している「雨宮 紫苑」という名前に「これはハンドルネームなの?」という興味を持ったのが起点で、調べてみたところ本も上梓されていて、タイトルが面白そうだったので読んでみた。

ちなみに、Amazonのレビューは両極端に分かれているが、個人的には非常に具体的で生活感があり、かつ論理的で歯に衣着せぬ物言いが面白かった。著者が日本にあまり馴染めず、ドイツ定住に活路を見出したことから、日本3:ドイツ7くらいの割合で各々の良さを記載している。
Amazonレビュー一部抜粋
- ドイツでの体験やドイツ人等とのコミュニケーションを通じて、日本とドイツとの違いに鋭く切り込んでいる
- 記者や学者が書くような文章と違い、両方を経験したからこそ話せる体験記が本書の魅力
- 個人の妄想に対して妄想で反論するという構図が延々と続きます。
- 著者のドイツ礼賛・日本批判の文章の押し付けに 読み切るのが苦痛でした。
あらすじ
「日本人とドイツ人は似ている」――何となく日本人は勝手に思っているけれど、実際にドイツに住んでみるとまったくのウソでした! 電車で「座りたいから席を譲ってほしい」と堂々と言ったり、簡単には非を認めなかったりするメンタル。安易にマネしないほうがいい「働き方」や教育制度。比べるうちに見えてくる日本の強みと弱点とは? 20代の若き感性が現地で驚き戸惑い怒り笑いながら綴る、等身大の比較文化論。
日本とドイツの違いに関して
- 交通機関・物流
- ポップカルチャー・おもてなし
- 部活
- 働き方改革・生産性・雇用(メンバーシップ or ジョブ型)
- 教育格差
- 恋愛・結婚・家族
- 空気を読む・マナー
など様々な角度から比較して論じているが、個人的に気になったところをピックアップ
知的好奇心のための旅行需要に応えられていないインバウンド観光
著者は、ドイツ人は日本人と比較して、旅行前にきっちりと歴史や関係人物の経歴を予習し、現地でも解説文をしっかりと読みこむという知的好奇心を満たす目的で旅行に訪れる人が多いと説いている。比して日本はどちらかというと、観光地をハシゴして写真を撮るというスタイルが多い。
という違いから、実は結構多くの外国人が日本のメジャーな観光地だけではなく、マイナーな観光地にも来ているので、地域的にももっとインバウンド観光を伸ばす余地はありそうだ。
ちなみに、現在コロナ明け+円安が相まって、インバウンド需要は増えていて、インバウンドだけで見るとサービス収支はプラスである。それに関する記事は下記。
ただ、日本独特の文化(温泉・着物など)が外国人に正確に伝わり切っていないことが多く、それが原因で下記のように外国人が怖がって文化体験をしない場合があり、日本のせっかくの良さが最大限に活かされていないとのこと。
だが、ネガティブな意味での「わからない」も多かった。「温泉に行こう」と誘っても「入り方がわからない。
【日本人とドイツ人】比べてみたらどっちもどっち。雨宮 紫苑
まわりから変な目で見られると面倒だからやめておく」と言われたし、「浴衣を着よう」と言っても「着方がわからない。うっかり脱げたら困るからいいや」と言われてしまった。
確かに一理ありそうだ。これに関しては、雨宮さんのような外国に移住もしくは定住した人が、養った比較文化の視点で日本の旅館や観光業界の外国人へのメッセージをコンサルするのが最適解なのではと思った。日本にいたままだと、どうしても、これは当たり前と思ってしまって、無意識のうちに説明を端折ったり、何をもっと分かりやすく外国人に説明したりPRしたりすれば良いのかが当の本人も分からない場合が多いだろう。
部活とフェアアイン
著者は部活に対しては、下記理由から「正直部活なんてなくなってしまえばいい」と主張している。
学生のうちから「先輩の言うことは絶対」「雑用は後輩の仕事」といった理不尽に慣れてしまうと、将来社会人になっても「理不尽は当然で受け入れることなんだ」と思い込んでしまいそうだ。「自己犠牲は美しい」と認識することで、定時で帰宅する人を「ズルい」と思ったり、「有給休暇取得は怠慢」という思考回路にならないだろうか、心配である。
部活における美徳が、このところよく議論されている日本人の生産性の低さの一因になっている……と言ったら、こじつけすぎだろうか。
【日本人とドイツ人】比べてみたらどっちもどっち。雨宮 紫苑
確かに、中学高校だと部活以外の選択肢が日本ではほとんどなく、部活に入るのが当たり前的な空気感があり、その部活では特に体育会系では上下関係が厳しく理不尽なこともあったりする。
私は中高時代サッカー部に所属していたが、もし今中学生に戻ったらおそらく体育系の部活には入らないだろう。
ドイツには、日本的な部活はない。そのかわり、フェアアイン(Verein)がある。
学校主体で同年代だけが集まる部活とは違い、市民クラブみたいなもの。
この市民クラブのいいところは、学校外に居場所を見つけられること、そしていろんな人と交流できることだ。
この仕組みはとても良いと感じた。確かに中高時代に親や教師以外で、様々な年上の大人と触れる機会はないので、そもそもどんな将来像を描けばいいのかすら分からない。特に田舎の場合はそうで、自分の場合もそもそもどんな職業があるのか、コンサルや商社というキーワードすら知らなかった。もちろん知らなかったので選択肢に入らなかった。
ジョブ型とメンバーシップ型の功罪
これは度々日本でも議論に上がる「日本もメンバーシップ型からジョブ型にせよ」に関するもの。
ドイツはジョブ型を採用しているが、ジョブ型の功罪を肌感覚ある感じで記載している。
たしかにドイツはプロフェッショナル志向ではあるが、そのぶん浅く広い知識と経験を持ったジェネラリストが少なく、ひとつの職種しかしない、できない人が多い。自分の仕事以外にはみんな無関心だから、関係のない仕事を手伝ったり便宜を図ってあげようといったこともあまりない。それは、必ずしもいいことだとは言えないだろう。
【日本人とドイツ人】比べてみたらどっちもどっち。雨宮 紫苑
確かに、これは良く言われるジョブ型のデメリットで、「それは私の仕事ではないのでやりません」となるので、部門間でこぼれ落ちてしまうようなタスクの拾い上げができずに、滞ることもありそうだ。
ちなみにドイツではジョブ型ではなく、ジェネラリスト型を育成すべきだという論調も見られるらしい。隣の芝生は青い。
また、職能給の場合、仕事によって給与がある程度決まっており、転職しても仕事内容が同じであれば大幅に給与が下がることはない。同じ仕事をしている人には同じ給与をというのが基本的な考え。
日本では終身雇用制で年齢が上がれば自然と給与も上がっていくのに対して、ドイツでは40歳程度で昇給しなくなり、同一の仕事になるので、給与も頭打ちになる人が多いとのこと。
つまりドイツでは、大半の人は四〇歳程度で昇給しなくなる一方で、肩書きを手にする一部の人は継続的にキャリアアップしていくのだ。どちらの割合が多いかといえば、もちろん前者である。
【日本人とドイツ人】比べてみたらどっちもどっち。雨宮 紫苑
日本だとジョブ型は業務委託のフリーランスに近そうである。デザイナーやエンジニアでフリーランスで業務委託をする人は日本でも増えてきている印象だが、スキルベースでの採用になるので、業務委託契約をした会社で、新しいスキルや言語に挑戦する / マネジメントにも挑戦する など何か新しいことに挑戦し続けない限り、おそらく給与アップは難しい。最初は、同じスキルをより先鋭化させていく必要があるが、10年もすれば頭打ちになりそうである。