第155回芥川賞受賞された、村田 沙耶香さんの小説「コンビニ人間」の感想を記載。
3年ほど前に読んで、今回再読。
あらすじ
36歳未婚、彼氏なし。コンビニのバイト歴18年目の古倉恵子。正規の就職をせずに大学時代に始めたコンビニのアルバイトを18年間続けていた。
古倉は子供の頃から変わり者で人間関係は希薄、恋愛経験も皆無だったが、「コンビニで出会う人間の真似」をしたり、妹の助言を聞くことで、大学生になってようやく普通の人間らしく振る舞う方法を身につけた。これまで世間一般の人間の規格から外れていた彼女にとって、これは「初めて私が人間として誕生した瞬間」であった。 ある日、婚活目的の新入り男性・白羽がやってきて、そんなコンビニ的生き方は恥ずかしい、と突きつけられるが……。
普通とは何か?
普通とは何か?を問いている作品は多いが(水に性欲を感じる人を描いた、朝井リョウ著「正欲」など)、本作品も「普通」とは何か?を問いている。
性経験はないものの、自分のセクシャリティを特に意識したこともない私は、性に 無頓着 なだけで、特に悩んだことはなかったが、皆、私が苦しんでいるということを前提に話をどんどん進めている。たとえ本当にそうだとしても、皆が言うようなわかりやすい形の苦悩とは限らないのに、誰もそこまで考えようとはしない。そのほうが自分たちにとってわかりやすいからそういうことにしたい、と言われている気がした。
「コンビニ人間」村田 沙耶香
今は、多くの選択肢があり、生き方も多様になりつつあるが、それでも、多くの人が共有する「普通」の生き方があり、みんなで集まった時にはどうしても「普通」の話題になりやすい。その方が場が円滑に進むから。
そんな中、自分の理解の範疇では理解不能な人や人の生き方を見ると、どうしても拒絶反応を起こし、距離を置いてしまうか、興味の眼差しで介入し始め、なんとか理解可能な範疇に無理くりおさめこもうとする。その方が、自分にとって都合が良いから。
おそらく人間は、理解不能なものをそのまま理解不能の状態として、放置しておくことはできない生き物なのだろう。全員がそうとは限らないが、多くの人がそうであろう。なんとかして理解したいと思うか(大きなお世話なのだが)、それでも理解できないとなったら、拒絶してしまう。距離感が0 or 100であり、ムズカシイ。まるで、途中で同極同士で反発する磁石のようであり、S極に対してS極として興味を持って近づこうとするも、もちろん永遠に理解はできないので、途中で反発して遠ざかるかのようである。
皆、変なものには土足で踏み入って、その原因を解明する権利があると思っている。私にはそれが迷惑だったし、 傲慢 で 鬱陶しかった。あんまり邪魔だと思うと、小学校のときのように、相手をスコップで殴って止めてしまいたくなるときがある。
そうか。叱るのは、「こちら側」の人間だと思っているからなんだ。だから何も問題は起きていないのに「あちら側」にいる姉より、問題だらけでも「こちら側」に姉がいるほうが、妹はずっと嬉しいのだ。そのほうがずっと妹にとって理解可能な、正常な世界なのだ。
「コンビニ人間」村田 沙耶香
五感と無機質な表現が面白い
最初の一文が「コンビニエンスストアは、音で満ちている。」と聴覚から始まっているが、本作品を通じて、コンビニの無機質さと、聴覚をはじめとした五感の表現が多用されており、読んでいてコンビニがワクワクする場所だと想起させてくれる感じがした。
他にも個人的に、面白いと感じたフレーズを列挙
コンビニエンスストアは、音で満ちている。
こうして、また一つ、店の細胞が入れ替わっていく。
同じ制服を着て、均一な「店員」という生き物に作り直されていく
私の摂取する「世界」
私はコンビニからの天啓を伝達している
ここは強制的に正常化される場所なのだ。異物はすぐに排除される。
「コンビニ人間」村田 沙耶香
「細胞、摂取、異物、排除、正常化」など、無機質を表現するワードが散りばめられており、かつ、本人が過干渉しない無機質な世界を、「私は店員になり、世界の歯車になれる。そのことだけが、私を正常な人間にしている」と肯定どころか、同化している部分が印象深い。
本人の無機質さ(行間を読まずに(めずに)、相手から受けた言葉通りの行動をする。相手に関して怒りの感情がわかないなど)を、淡々と否定的でも肯定的でもなく描いており、そうした本人の人物像が、コンビニの無機質さと重なっていて、調和している。
主人公は、「個」を本来それほど必要とされないコンビニという世界の中で、圧倒的に輝いており、かつ、それが本人のアイデンティティにもなっており、生きる意味を与えてくれるコンビニという存在はすごいという読後感があった。
私にはコンビニの「声」が聞こえて止まらなかった。コンビニがなりたがっている形、お店に必要なこと、それらが私の中に流れ込んでくるのだった。
「コンビニ人間」村田 沙耶香
もはや、拠り所のレベルとして、宗教の域だが、逆にそこまで拠り所とできる存在を持てる(紆余曲折あり、再実感した)主人公は、素晴らしい人生なんだろうなと感じた。この後も、コンビニ人間として人生の幸せを突き進んでいきそうである。
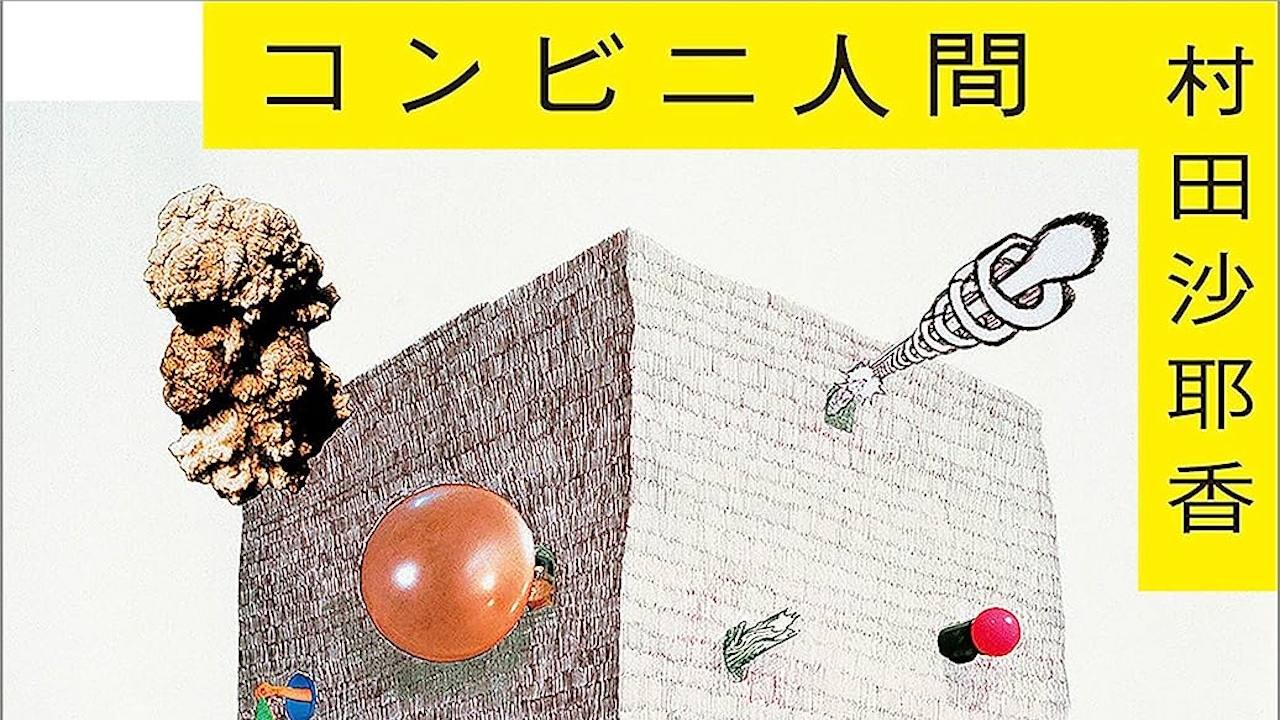

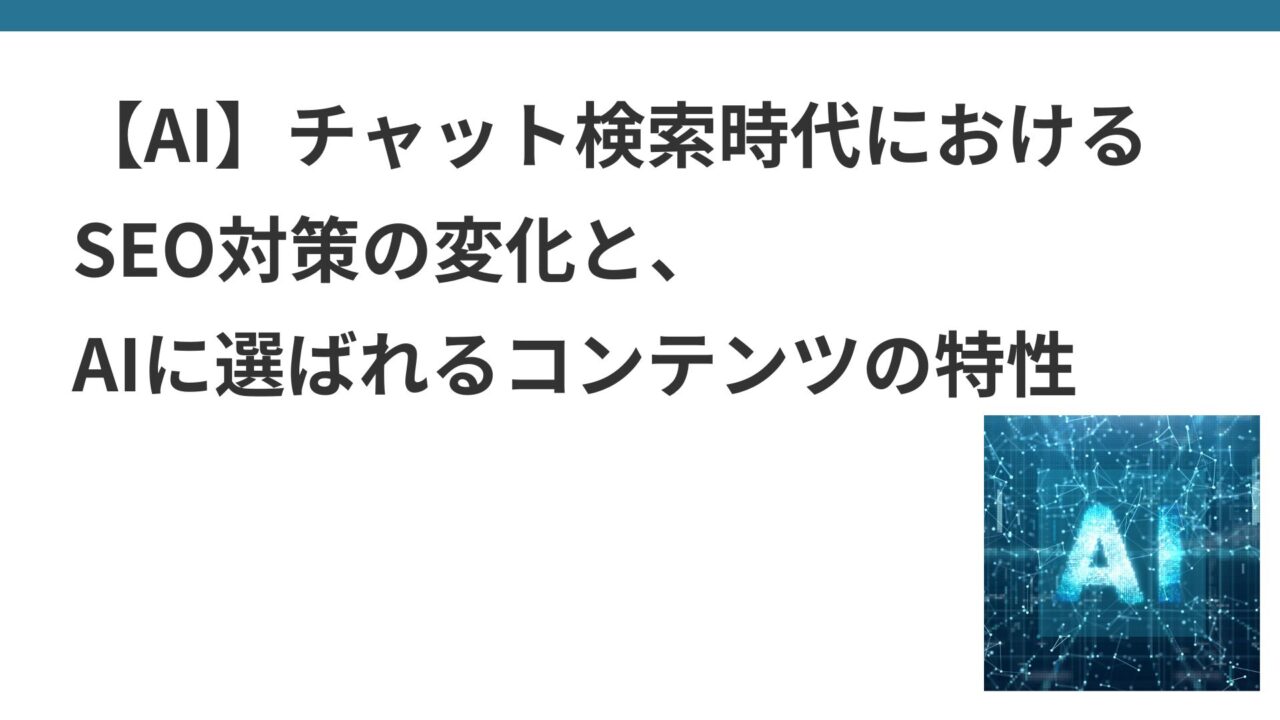
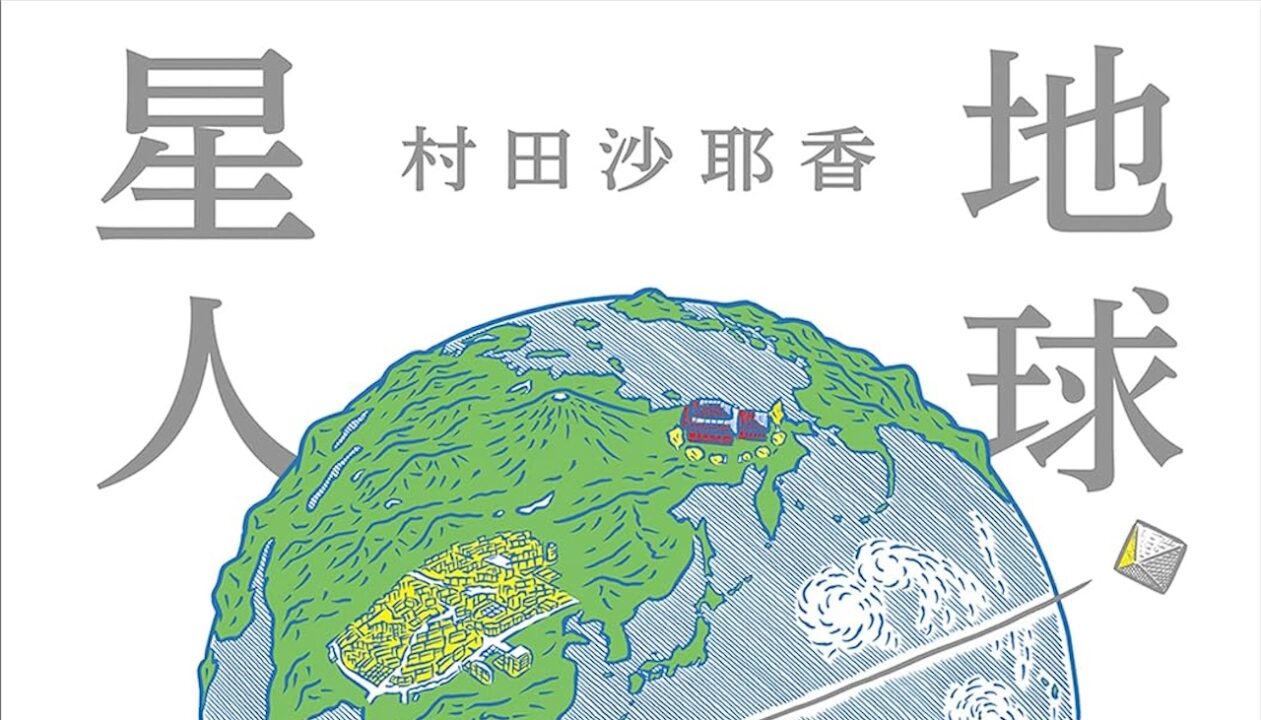
コメント